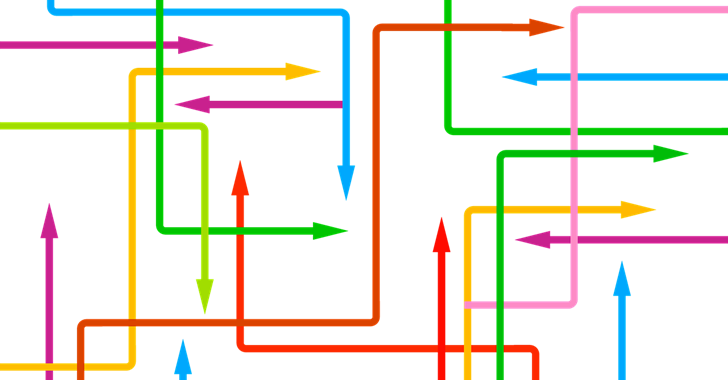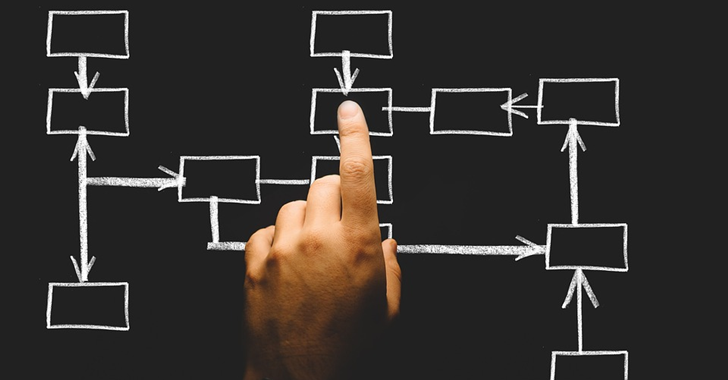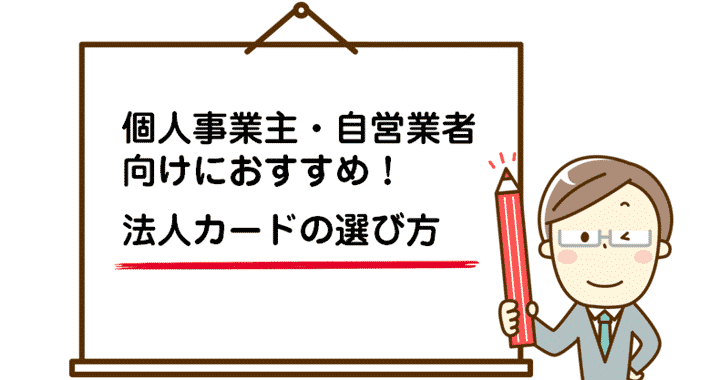個人の印鑑証明書と同じように、印鑑証明(正確には印鑑証明書)を発行するためには、事前に印鑑を登録→印鑑登録カード取得の申請→印鑑証明書の交付申請を行うという流れになります。
それ程難しい流れではないですが、印鑑証明書取得の手続きがわからなくて悩んでおられる方は実際に多いです。又、個人の印鑑証明書とは異なる箇所もありますので、その点も含めて、法人の印鑑証明の登録方法・取り方・場所・手数料・手順まで、説明したいと思います。
法人の印鑑証明で悩みやすい5つのポイントを徹底解説
放任の印鑑証明発行する悩みやすい5つのポイント(法人の印鑑証明の登録方法、法人の印鑑証明の取り方、法人の印鑑証明の取得場所、法人の印鑑証明の手数料、法人の印鑑証明の手順)を以下でわかりやすく、分けて解説します。
法人の印鑑証明の登録方法(誰が取得できるのか、必要な持ち物)
法人の印鑑証明書を取るには、後ほど詳しく述べますが、法務局に行く場合と郵送での場合の2つから選べます。
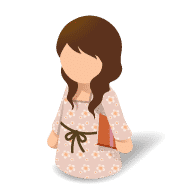
法人の印鑑証明書を取得する際に法務局に行く場合、代表以外の代理人でも請求は可能です。(ただし、会社の情報を記入する事が必要になるので、会社の経営陣が理想です。)
又、委任状などもに関しても事前に用意する必要ありません。しかし、気をつけなければならない点として、印鑑カードが必要という点です。
印鑑カードとは
印鑑登録カードとは、会社の代表者が登記所に印鑑を提出し印鑑登録を行う際、登記所に印鑑カード交付申請を行うことによって交付を受けることができる印鑑登録を証明するカードのことを指します。もし、会社を設立し、且つ法人登記が完了し、実印を作ると、登記所から印鑑カードが貰えます。又、この印鑑登録カードは、会社の代表者が印鑑証明書の交付を受ける場合には、必ず必要となります。
以下の2点(印鑑カードを紛失と添付書類と部数)に関しては、法人の印鑑証明の登録をする際、多くの人が過ちないし、間違えやすい点なので、気をつけてください。
<印鑑カードを紛失に関して>
印鑑カードを紛失又は破損し、再度、印鑑カードを発行する場合は,紛失(又は破損)したカードについての印鑑カード廃止届書と新たにカードを発行するための印鑑カード交付申請書を提出する必要が出てきます。
上記の2点(印鑑カード廃止届書と印鑑カード交付申請書)の手続の際、登記所への届出印のほかは特にありません。しかし、もし代理人が手続する場合に関しては『印鑑カード廃止届書』と『印鑑カード交付申請書』の委任状の欄に必要事項を記載、登記所への届出印を押印という2つの手続きをする必要があります。
また、印鑑カードの廃止手続に関しては、印鑑届出者本人又は代理人について、本人であることの確認が必要になります。そのため、運転免許証等の本人確認ができるものを持参しましょう。
<添付書類と部数に関して>
添付書類と部数に関しては特に以下の2点に注意しなければいけません。
- 代理人が印鑑カード交付申請、印鑑(改印)届又は印鑑・印鑑カード廃止届をする場合には,委任状が必要です。
- 印鑑(改印)届には,市区町村長作成の印鑑証明書が必要です。
法人の印鑑証明の取得場所、取り方、取得の手順
先程、個人の印鑑証明書とは異なる箇所もあると言いましたが、具体的に異なる点の一つとして、登録場所が挙げられます。個人の印鑑登録の場合、市区町村で行いますので、皆さんも経験はあると思います。しかし、法人の印鑑登録の場合は、印鑑届書を法務局に提出しなければなりません。
というのは、法律(商業登記法第20条において、登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等、その他の法人の場合は理事等)は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならない)と記載されているため、必ず、法務局にて提出しなければなりません。ただ、印鑑登録申請は会社設立と同時に行うことが多いと思います。そのため、法人の印鑑登録を登記の申請と同時に提出することが賢明です。
以下は東京都又は、東京近郊の年にある法務局、出張所も一覧になります。これから、法人の印鑑証明を取得する際は、自分のオフォスからどこの法務局が近いのかを以下の一覧表で参照しましょう。
| 法務局名 | 住所 | 最寄り駅 | 証明書請求発行機 |
| 東京法務局 | 千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎 | 各線:九段下駅 | 〇 |
| 東京法務局 港出張所 | 港区東麻布2丁目11番11号 | 各線:麻布十番駅 地下鉄日比谷線:神谷町駅 |
〇 |
| 東京法務局 渋谷出張所 | 渋谷区宇田川町1番10号(渋谷地方合同庁舎) | 各線:渋谷駅 | 〇 |
| 東京法務局 新宿出張所 | 新宿区北新宿1丁目8番22号 | 各線:大久保駅 JR山手線:新大久保駅 |
〇 |
| 東京法務局 豊島出張所 | 豊島区池袋4丁目30番20号(豊島地方合同庁舎) | JR各線:池袋駅 | 〇 |
| 東京法務局 台東出張所 | 台東区台東1丁目26番2号 | JR各線:秋葉原駅、御徒町 地下鉄各線:秋葉原駅、仲御徒町駅、上野御徒町駅、末広町駅 |
〇 |
| 東京法務局 墨田出張所 | 墨田区菊川一丁目17番13号 | JR各線:両国駅、錦糸町駅 地下鉄各線:森下駅、菊川駅 |
〇 |
| 東京法務局 品川出張所 | 品川区広町2丁目1番36号(品川区総合庁舎) | 各線:大井町駅 東急線:下神明駅 |
〇 |
| 東京法務局 中野出張所 | 中野区野方1丁目34番1号 | JR中央線:中野駅 西武新宿線:野方駅 |
〇 |
| 東京法務局 城南出張所 | 大田区鵜の木2丁目9番15号 | 東急多摩川線:鵜の木駅 | 〇 |
| 東京出張所 世田谷区役所 | 世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎2階 | 東急世田谷線:松陰神社前駅 | ✕ |
| 東京法務局 杉並出張所 | 杉並区今川2丁目1番3号 | 各線:荻窪駅 西武新宿線:上井草駅 |
✕ |
| 東京法務局 練馬出張所 | 練馬区春日町5丁目35番33号 | 都営大江戸線:練馬春日町駅 | 〇 |
| 東京法務局 板橋出張所 | 板橋区板橋1-44-6 | 都営三田線:新板橋駅 JR埼京線:板橋駅 東武東上線:下板橋駅 |
〇 |
| 東京法務局 北出張所 | 北区王子6丁目2番66号 | 各線:王子駅 都電荒川線:王子駅前駅 |
✕ |
| 東京法務局 城北出張所 | 葛飾区小菅4丁目20番24号 | 東京メトロ千代田線:綾瀬駅 | ✕ |
| 東京法務局 江戸川出張所 | 江戸川区中央1丁目16番2号 | JR線:新小岩駅 各線:葛西駅・西葛西駅・船堀駅 |
〇 |
| 東京法務局 町田出張所 | 町田市森野2丁目28番14号 町田地方合同庁舎 | 各線:町田駅 | 〇 |
| 東京法務局 立川出張所 | 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎)6階 | 各線:立川駅 多摩モノレール:立川北駅 |
〇 |
| 東京法務局 田無出張所 | 西東京市田無町4丁目16番24号 | 西武新宿線:田無駅 | ✕ |
| 東京法務局 府中支局 | 府中市新町2丁目44番地 | 各線:府中駅 JR中央線:武蔵小金井駅 |
〇 |
| 東京法務局 八王子出張所 | 八王子市南大沢2丁目27番地 フレスコ南大沢10・11階 | 京王相模原線:南大沢駅 | 〇 |
| さいたま地方法務局 本局 | さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎) | JR埼京線:与野本町駅 | 〇 |
| 千葉地方法務局 本局 | 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 | JR京葉線:千葉みなと駅 JR総務線:千葉駅、市役所前駅 |
✕ |
| 横浜地方法務局 本局 | 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 | みなとみらい線:馬車道駅 各線:桜木町駅 |
✕ |
法人の印鑑証明の取得場所
法人の印鑑証明の取得場所を紹介しますが、まず、法人の印鑑証明の取得場所以前に、法人の印鑑証明を取得する方法は、①法務局(登記所)と②郵送の2つに分けられます。
では、それぞれについて、取得方法を見ていきましょう。
①法務局(登記所)
まずは、法務局での取得方法を説明します。
まず、最寄りの法務局を調べ、実際に法務局の窓口へ出向きましょう。そして、申請に関してですが、情報がデータ化されたことにより、全国のどの法務局(出張所でも)からでも法人の印鑑証明自体は取得できるようになっています。
※ただ、各地の法務局についてのそれぞれ注意点などがあるため、詳しくは以下の法務局のホームページを参照お願いいたします。
※又、取得可能時間は8:30~17:15で且つ、休みは土日祝と年末年始となっているので、平日の17時前までには、法務局に着くようにスケジューリングしましょう。
※印鑑カードがあれば、法人の代表者でなくとも委任状なしで取得可能になります。
法務局で法人の印鑑証明を取得する場合、印鑑証明を請求する方法は以下の2つの方法があります。
(1)まずは、窓口で申請書を書いて請求する方法
(2)次に、機械を使用して請求する方法(ただ、機械がある法務局は一部になります。詳しくはホームページにて確認しましょう。)
(1)窓口で申請書を書いて請求する方法
では、まず窓口で申請書を書いて請求する方法について説明します。窓口で申請書を書いて請求する場合、まず、
- 法務局に備え付けてある申請書(登記事項証明書等交付申請書と呼ばれるものです。)に必要事項を記入します。
- 次に、1通450円分の収入印紙を購入し、登記事項証明書等交付申請書とともに窓口に提出します。
※申請書には、会社の商号、会社の住所、印鑑提出者の資格、氏名、生年月日の記入が必要になります。
(2)機械を使用して請求する方法
次に、機械を使用して請求する方法を説明します。法務局に設置されている機械(証明書発行請求機。と呼ばれるものです)を使って請求する場合、申請書を書く手間が省けるのに加え、印鑑証明発行までの待ち時間が少なくなる(約10分程度かかります。)、という利点がありますが、先ほども述べたように、機械を使用して請求する場合、機械がある法務局は一部のみなので、注意が必要です。
機械を使用して請求する流れは主に以下の3通りになります。
- まず、印鑑カードを挿入して、請求機へ情報を入力します(※印鑑登録者の生年月日が必要になります。そのため、代理で取得される場合は事前に印鑑登録者の生年月日を把握しておきましょう)。
- 次に、1通450円分の収入印紙の購入を購入します。
- 最後に、窓口にて印鑑証明を受け取ります。
②郵送
次に郵送にて、法人の印鑑証明する方法を説明します。法人の印鑑証明を郵送してもらうためには、以下の2つの方法があります。
- 必要書類を郵送し、登記簿を返送してもらう方法
- オンラインにて請求する方法
では、それぞれについて説明します。
(1)必要書類を郵送し、印鑑証明を返送してもらう方法
では、必要書類を郵送し、印鑑証明を返送してもらう方法から説明します。もし、印鑑証明を返送してもらいたい場合、下記のものを用意し、法務局に郵送すれば、法務局から印鑑証明を返送してもらうことができます。
以下の4点になります。
- 印鑑証明書交付申請書(ホームページからダウンロード)
- 印鑑カード
- 切手を貼付した返信用封筒
- 収入印紙450円/通
(2)オンラインにて請求する方法
オンラインにて請求したい場合は申請用総合ソフトを利用して請求することができます。請求した印鑑証明は、郵送または窓口にて受け取ることができるので、安心です。
しかし、オンラインにて請求する方法の場合、申請用の総合ソフトは登記や供託のためのソフトくです。そのため、印鑑証明を発行するためだけに利用するには設定がやや長く、面倒であると多くの人は感じているようです。結論として、他のサービスも利用する機会があるのであれば、登録しておいて問題ないです。しかし、一方で印鑑証明のみを請求する場合、窓口や郵送で請求する方が賢明かもしれません。
※しかし、もし、受け取り場所を法務局や法務局サービスセンターにした場合、取得可能時間は平日8:30~21:00になるので、注意が必要です。
法人の印鑑証明の手数料
法人の印鑑証明書を取得するには、手数料がかかります。印鑑証明書の交付に関しては、1通450円ですが、そのほかの交付を行う場合、当たり前ですが、別途お金がかかります。印鑑証明書の交付に関しては、1通450円ですが、設立する場合、書類を発行しなければ、いけないので、余分にお金を持っていきましょう。
以下が 書類の金額一覧です。自分の会社の場合、何円必要になるのかということを法人の印鑑証明書を取得する際に必ず確認しましょう。
| 種別 | 冊数 | 金額(税込) |
| 会社・法人の登記簿謄抄本又は登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)の交付 | 1通 | 600円 (1通の枚数が50枚を超えるものについては,600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額) |
| 登記事項要約書の交付 | 1通 | 450円 (1通の枚数が50枚を超えるものについては,600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額) |
| 登記簿又は登記申請書の閲覧 | 1登記用紙 | 450円 |
| 資格証明書(登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明)の交付 | 1通 | 450円 |
| 印鑑証明書の交付 | 1通 | 450円 |
まとめ
法人の印鑑証明の登録方法や、法人の印鑑証明の取得場所、取り方、取得の手順、法人の印鑑証明の手数料について書きましたが、特に法務局に行かれる場合は提出書類などはそれぞれの注意点で述べたように、規則などが多く存在します。それぞれの規則に関して、再度チェックし、法人の印鑑証明を取得できるように備えましょう。